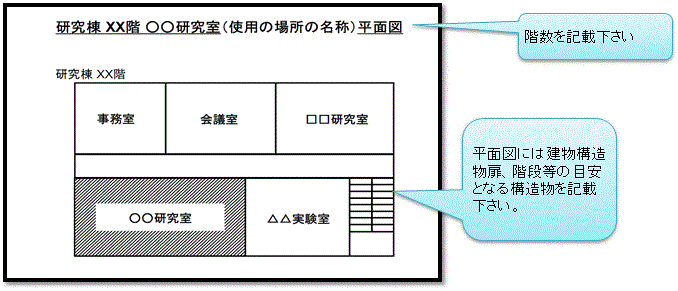2-1.国際規制物資の使用許可申請の作成について
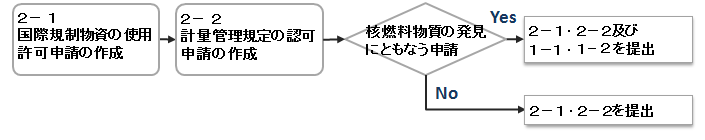
- 2-1.国際規制物資の使用許可申請の作成について
- 2-2.計量管理規定の認可申請の作成について
国際規制物資使用許可申請書の作成にあたっては、下記のファイル(MS-Excel)をダウンロードしていただき、各シートに必要事項を入力します。
既に、「核燃料物質事故増加報告書入力シート」を作成するため下記のファイルをダウンロード済みの場合は、ダウンロード済みのファイルを利用します。
基礎情報入力シートについて
ダウンロードしたファイルから、「基礎情報入力シート」を選択し、ピンク色セルに法人情報、使用場所等に関する情報を入力します。
1-2.核燃料物質事故増加報告書の作成について において、基礎情報入力シートを作成済みの場合には、改めて入力する必要はありません。
これらの情報は、必要に応じIAEAに提出することから、氏名等については英語表記を記載していただくこととしております。
「使用許可申請書入力シート」に必要事項を記入後、原子炉等規制法第61 条の4 の欠格事項にあたらないことの宣誓書、使用の場所を示す図面(案内図、建物配置図、平面図)を作成し、原子力規制委員会宛に申請します。
使用許可申請書入力シートについて
ダウンロードしたファイルから、「使用許可申請書入力シート」を選択し、ピンク色セルに、核燃料物質の区分、数量を入力します。
なお、「基礎情報入力シート」に入力した内容は、「使用許可申請書入力シート」の水色セルに自動的に反映されるようリンクを貼っています。内容に誤りがないことをご確認下さい。修正が必要な場合には、「基礎情報入力シート」にて修正して下さい。
- 核燃料物質の区分は、使用する核燃料物質の種類によって天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれかを判断します。複数の区分を選択することが可能です。
管理下にない核燃料物質を発見し、これを保管管理する場合には、発見した核燃料物質の区分に応じ天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれかを選択します。なお、複数の核燃料物質を発見した場合は、複数の区分を選択します。 - 数量は、原子炉等規制法で認められた国際規制物資の使用許可の最大値を記入し申請することが可能です。
実際に使用する数量を超え、天然ウラン、劣化ウランについては、それぞれ最大300gで、トリウムについては最大900gで許可をとることができます。 - 使用目的、使用方法は、研究目的で新たに核燃料物質を使用する場合と、管理下にない核燃料物質を発見し、これを保管管理する場合で記載内容が異なります。
管理下にない核燃料物質を発見し、これを保管管理する場合には、白色セルに記載のとおり(変更せず)とします。
なお、研究目的で新たに核燃料物質を使用する場合には、使用目的を「電子顕微鏡用試料の染色」、「トリウム合金の物性研究」、使用の方法を「ウラン化合物を水溶液にして使用する(2%に希釈)」、「蒸留水で2%に希釈し染色」、「トリウムと他の金属の合金を作製し、電気抵抗・磁性等の物性を測定する」等具体的な使用目的、使用方法を記入して下さい。 - 未登録の核燃料物質として新たに発見された場合には、使用目的は明確でないことから「試薬の保管管理」となります。使用方法は「計量管理規定に従い保管管理」となります。
- 工場又は事業所長が代表者より委任されている場合には、委任状(代表取締役社長から工場長(研究所長等)への委任)を添付して下さい。
宣誓書作成シートについて
ダウンロードしたファイルから、「宣誓書」シートを選択し、原子炉等規制法第61 条の4で定める許可の欠格条項に該当しないことを確認して下さい。
なお、「基礎情報入力シート」に入力した内容が、「宣誓書入力シート」の水色セルに自動的に反映されるようリンクを貼っています。内容に誤りがないことをご確認下さい。修正が必要な場合には、「基礎情報入力シート」にて修正して下さい。
欠格条項
- 国際規制物資の使用の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
- 原子炉等規制法又は原子炉等規制法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、二年を経過していない者
- 成年被後見人
- 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記の三項目のいずれかに該当する者のあるもの
使用の場所を示す図面について
使用の場所を示す図面として、最寄り駅から工場又は事業所までの経路がわかる案内図、使用の場所を含む工場又は事業所の全体がわかる建物配置図、使用の場所がわかる平面図の3種類を用意して下さい。
案内図(例)
最寄り駅から工場又は事業所までの経路がわかる図面を用意して下さい。
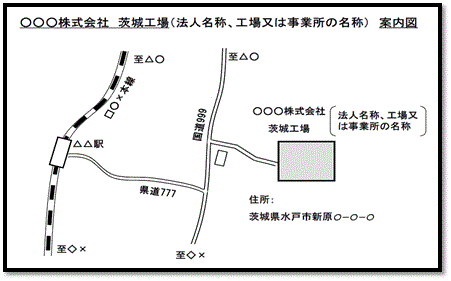
建物配置図(例)
使用の場所を含む工場又は事業所の全体がわかる図面を用意して下さい。
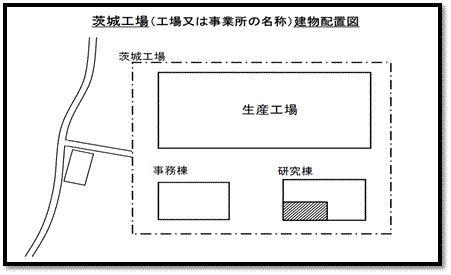
平面図(例)
使用の場所がわかる図面としてください